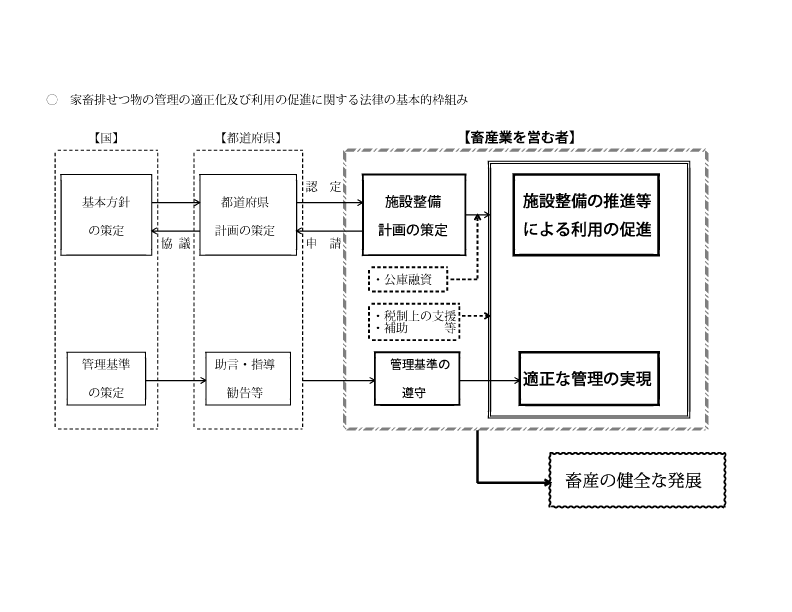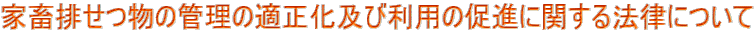
1.基本的考え方
(1)家畜排せつ物は、これまで、畜産業における資源として、農産物や飼料作
物の生産に有効に利用されてきたところである。
(2)しかしながら、近年、畜産経営の急激な大規模化の進行、高齢化に伴う農
作業の省力化等を背景として、家畜排せつ物の資源としての利用が困難にな
りつつある一方、地域の生活環境に関する問題も生じている。
(3)他方、我が国全体において資源循環型社会への移行が求められるとともに
国民の環境意識が高まる中で、家畜排せつ物について、その適正な管理を確
保し、たい肥として農業の持続的な発展に資する土づくりに積極的に活用す
るなどその資源としての有効利用を一層促進する必要がある。
(4)このため、畜産業における家畜排せつ物の管理の適正化を図るための措置
及び利用を促進するための支援措置を講ずることにより、我が国畜産の健全
な発展を図るものとする。
2.法律の概要
(1)家畜排せつ物の管理の適正化のための措置
○ 管理基準の遵守
ア農林水産大臣による家畜排せつ物の処理・保管施設の構造基準等を内容
とする管理基準の策定
イ畜産業を営む者による管理基準に則した家畜排せつ物の管理
ウ都道府県知事による必要な指導・助言、勧告・命令(一定の規模以下の
者を除く)の実施
(2)家畜排せつ物の利用の促進のための措置
① 基本方針の策定
農林水産大臣による家畜排せつ物の利用の促進に関する基本方針の策定
② 都道府県計画の作成
都道府県による地域の実情に即応した施設整備の目標等を内容とした計画
の作成
③ 金融上の支援措置
ア畜産業を営む者の作成する施設整備計画の認定(都道府県知事)
イアの認定を受けた者に対する農林漁業金融公庫の融資
(施設の取得等に必要な資金のほか、施設・機械の賃借料の全額一括支払
い等に必要な資金を融通)
(参考)その他関連税制・予算措置
① 税制上の支援措置
ア所得税・法人税
家畜排せつ物のたい肥化施設等に対する特別償却(16%)の適用
イ固定資産税
家畜排せつ物のたい肥化施設等に対する固定資産税の特例(法律の施行
後平成16年3月31日までの間に取得された施設について、5年間課税
標準1/2)
② 予算措置
ア環境保全型畜産確立対策事業(非公共事業)
家畜排せつ物のたい肥化施設等の整備、たい肥の流通の促進、家畜排せ
つ物の利用技術の実用化等を実施(11年度予算額34億円)
イ畜産環境整備事業(公共事業)
家畜排せつ物のたい肥化施設等の整備、還元用草地・周辺環境の整備を
実施(11年度予算額48億円)
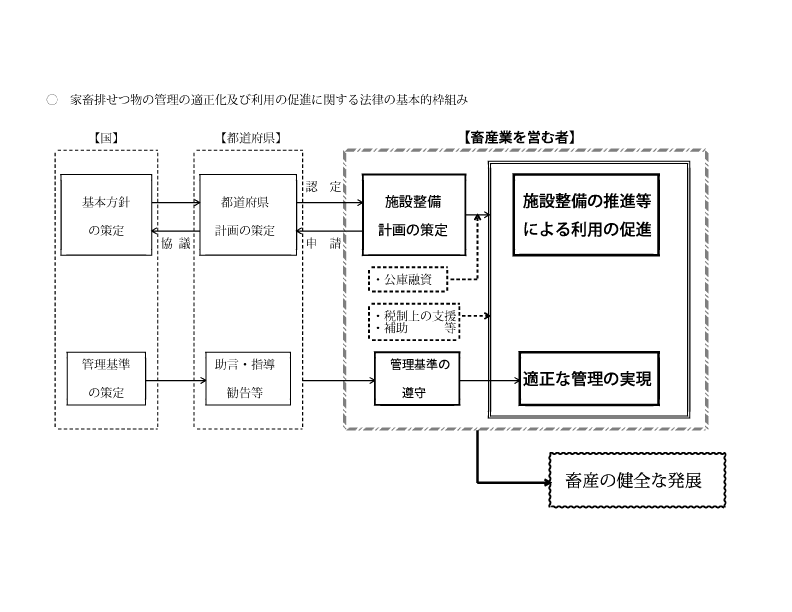
【ふん尿法】
最終改正:平成一三年四月一一日法律第28号
(目的)
第1条
この法律は、畜産業を営む者による家畜排せつ物の管理に関し必要な事項を定めるとともに、家畜排せつ物の処理の高度化を図るための施設の整備を計画的に促進する措置を講ずることにより、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進を図り、もって畜産業の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「家畜排せつ物」とは、牛、豚、鶏その他政令で定める家畜の排せつ物をいう。
(管理基準)
第3条
農林水産大臣は、農林水産省令で、たい肥舎その他の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設の構造設備及び家畜排せつ物の管理の方法に関し畜産業を営む者が遵守すべき基準(以下「管理基準」という。)を定めなければならない。
2 畜産業を営む者は、管理基準に従い、家畜排せつ物を管理しなければならない。
(指導及び助言)
第4条
都道府県知事は、家畜排せつ物の適正な管理を確保するため必要があると認めるときは、畜産業を営む者に対し、管理基準に従った家畜排せつ物の管理が行われるよう必要な指導及び助言をすることができる。
(勧告及び命令)
第5条
都道府県知事は、前条の規定による指導又は助言をした場合において、畜産業を営む者がなお管理基準に違反していると認めるときは、当該畜産業を営む者に対し、期限を定めて、管理基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、当該者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(報告の徴収及び立入検査)
第6条
都道府県知事は、前2条の規定の施行に必要な限度において、畜産業を営む者に対し、必要な報告を命じ、又はその職員に、畜産業を営む者の事業場に立ち入り、家畜排せつ物の処理若しくは保管の用に供する施設の構造設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(基本方針)
第7条
農林水産大臣は、家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 家畜排せつ物の利用の促進に関する基本的な方向
二 処理高度化施設(送風装置を備えたたい肥舎その他の家畜排せつ物の処理の高度化を図るための施設をいう。以下同じ。)の整備に関する目標の設定に関する事項
三 家畜排せつ物の利用の促進に関する技術の向上に関する基本的事項
四 その他家畜排せつ物の利用の促進に関する重要事項
3 農林水産大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
4 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(都道府県計画)
第8条
都道府県は、農林水産省令で定めるところにより、当該都道府県における家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画(以下「都道府県計画」という。)を定めることができる。
2
都道府県計画においては、次に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、基本方針の内容に即するものでなければならない。
一 家畜排せつ物の利用の目標
二 整備を行う処理高度化施設の内容その他の処理高度化施設の整備に関する目標
三 家畜排せつ物の利用の促進に関する技術の研修の実施その他の技術の向上に関する事項
四 その他家畜排せつ物の利用の促進に関し必要な事項
3 都道府県は、都道府県計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、当該都道府県計画に定める前項第1号及び第2号に掲げる事項について、農林水産大臣に協議しなければならない。
4 都道府県は、都道府県計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、農林水産大臣に報告しなければならない。
(処理高度化施設整備計画の認定)
第9条
畜産業を営む者は、処理高度化施設の整備に関する計画(以下「処理高度化施設整備計画」という。)を作成し、これを当該処理高度化施設整備計画に係る処理高度化施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、当該処理高度化施設整備計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 処理高度化施設整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 処理高度化施設の整備の目標
二 処理高度化施設の整備の内容及び実施時期
三 処理高度化施設の整備の実施に伴い必要となる資金の額及びその調達方法
3 都道府県知事は、第1項の認定の申請があった場合において、その処理高度化施設整備計画が、都道府県計画に照らし適切なものであることその他の農林水産省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
(計画の変更等)
第10条
前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る処理高度化施設整備計画を変更しようとするときは、当該処理高度化施設整備計画に係る処理高度化施設の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けなければならない。
2 都道府県知事は、前条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る処理高度化施設整備計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定処理高度化施設整備計画」という。)に従って処理高度化施設の整備を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。
(農林漁業金融公庫からの資金の貸付け)
第11条
農林漁業金融公庫は、農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第355号)第18条第1項及び第4項、第18条の2第1項並びに第18条の3第1項に規定する業務のほか、第9条第1項の認定を受けた者に対し、認定処理高度化施設整備計画に従って処理高度化施設の整備を実施するために必要な長期かつ低利の資金であって他の金融機関が融通することを困難とするものの貸付けの業務を行うことができる。
2 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、農林漁業金融公庫が定める。
3 第1項の規定により農林漁業金融公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての農林漁業金融公庫法第12条の2第2項第1号、第29条、第30条第1項及び第35条第3号の規定の適用については、同法第12条の2第2項第1号中「又はこの法律」とあるのは「若しくは家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律
又はこれらの法律」と、同法第29条及び第30条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」と、同法第35条第3号中「第18条の3まで」とあるのは「第18条の3まで及び家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第11条第1項」とする。
(研究開発の推進等)
第12条
国及び都道府県は、家畜排せつ物のたい肥化その他の利用の促進に必要な技術の向上を図るため、技術の研究開発を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
(報告の徴収)
第13条
都道府県知事は、第9条第1項の認定を受けた畜産業を営む者に対し、認定処理高度化施設整備計画の実施状況について報告を求めることができる。
(経過措置)
第14条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(罰則)
第15条 第5条第2項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第16条 第6条第1項若しくは第13条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第6条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。
第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
附 則
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一三年四月一一日法律第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
【ふん尿法施行規則】
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第112号)第3条第1項、第8条第1項、第9条第3項及び第14条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則
を次のように定める。
(管理基準)
第1条
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項の管理基準は、次のとおりとする。
一 たい肥舎その他の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設(以下「管理施設」という。)の構造設備に関する基準
イ 固形状の家畜排せつ物の管理施設は、床を不浸透性材料(コンクリート等汚水が浸透しないものをいう。以下同じ。)で築造し、適当な覆い及び側壁を設けること。
ロ 液状の家畜排せつ物の管理施設は、不浸透性材料で築造した貯留槽とすること。
二 家畜排せつ物の管理の方法に関する基準
イ 家畜排せつ物は管理施設において管理すること。
ロ 管理施設の定期的な点検を行うこと。
ハ 管理施設の床、覆い、側壁又は槽に破損があるときは、遅滞なく修繕を行うこと。
ニ 送風装置等を設置している場合は、当該装置の維持管理を適切に行うこと。
ホ 家畜排せつ物の年間の発生量、処理の方法及び処理の方法別の数量について記録すること。
2 前項の規定は、その飼養する家畜の頭羽数が、牛及び馬にあっては十頭未満、豚にあっては百頭未満、鶏にあっては二千羽未満の畜産業を営む者については、適用しない。
(立入検査をする職員の身分証明書の様式)
第2条 法第6条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式による。
(都道府県計画)
第3条 法第8条第1項の都道府県計画は、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき作成するものとする。
2 都道府県は、法第8条第3項の規定により農林水産大臣に協議しようとするときは、その協議書に当該都道府県計画及びこれに定める法第8条第2項第1号及び第2号に規定する事項が適当であるかどうかを判断するために必要な事項を記載した説明書を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
(処理高度化施設整備計画の認定基準)
第4条 法第9条第3項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 処理高度化施設整備計画が都道府県計画に照らし適切なものであること。
二 処理高度化施設整備計画の達成される見込みが確実であること。
附 則
この省令は、法の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。ただし、次の各号の規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第1条第1項第2号ホの規定 平成十四年十一月一日
二 第1条第1項第1号及び第2号イの規定 平成十六年十一月一日
別記様式 (第2条関係)
【ふん尿法施行令】
内閣は、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第112号)第2条及び第11条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(家畜の範囲)
第1条
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条の政令で定める家畜は、馬とする。
(農林漁業金融公庫からの資金の貸付けの利率等)
第2条
法第11条第2項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については八年とする。
附 則
この政令は、法の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。
BACK
HOME
![]()